CASE:TwentyThree
第一幕
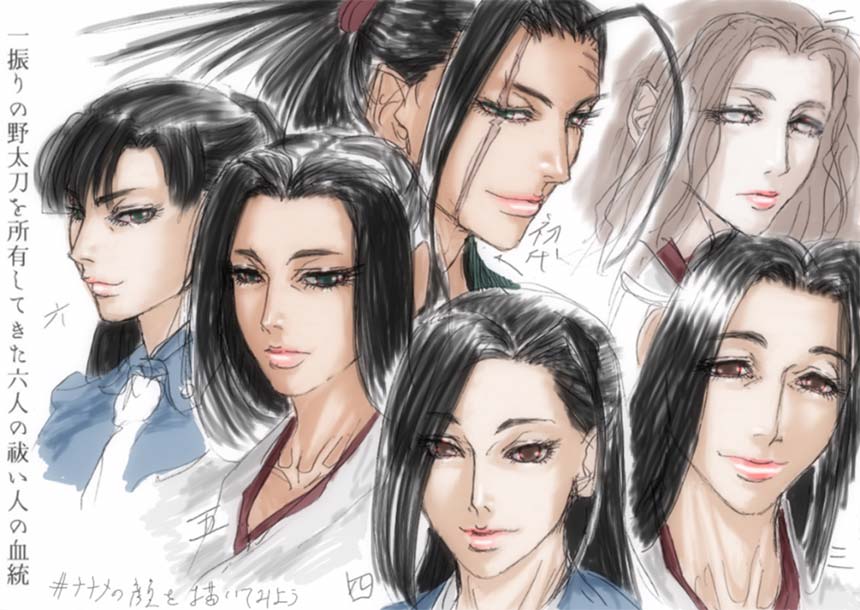
夜に向け宴の準備が進んでいた。
葵と裕子と、後は「何となく体が覚えていた」稜威雌も材料の下ごしらえ。
そして弥生は稜威雌のいつもの部屋を片付け座卓や座布団を幾つも並べている。
「あれ? そう言えば何でボク達こんなに一杯料理してるんだっけ」
概念一つで稜威雌の世界の中も調整出来る、今それは広くかまども沢山あり
それは祓いの力でどうとでも調理が出来る状態、水は買ってきた分もある。
裕子や稜威雌もふと
「…あら、そう言えば何故…」
「でも、何故でしょう、心が躍ります…」
稜威雌もいつになく浮き浮きしていた。
「さ、そろそろ来るわよ、まぁお酒やつまみで間は持たせられるけど」
弥生の言葉に葵が
「誰が来るんだっけ?」
「誰って、そりゃ」
と言いかけた時、稜威雌の世界本殿側からこちらへやって来る二人分の足音と
「おー、二代目! すっかり立派になって、悪かったね、引き継ぎが急だったのは」
弥生が振り返り
「先代、ま、色々あったけど正しく色々継げたわ、全ては見かねて声を掛けてくれた
貴女のお陰だわ、まー、色々乱れてるのは大目に見てよw」
五代弥生、そしてその横には、葵が目を輝かせ
「おやいさん! ボク会いたかったんだ! 凄く!」
一瞬調理も忘れて葵がおやいさんに駆け寄ると
「貴女のことはずっと二人で輪の外を巡りながら見てました、葵ちゃん、
私も会いたかったですよ」
握手やらナデナデやらで迎えつつおやいさんも調理に加わりつつ
「弥生さんは六代さんとお先にどうぞ」
「やー、悪いね、一緒に一杯引っかけたかったよ、もう少し時間掛けられたらさぁ」
六代弥生も調理場に「悪いわね」と言いつつ
「私もさ、稜威雌使いに直で師事したなんて前代未聞だろうし、積もるモノが沢山ある」
一足お先にと座に着き、つまみと共に酒は何を飲むかとか六代が聞くと麦酒と五代は言い
ビールをコップへ注ぎ「さぁどうぞどうぞ」と酒盛りが始まる。
五代と六代の「二人の弥生」は直接の師弟でもある、すっかり一人前の、
そして若干危ういながらもギリギリで道を踏み外すこともなく後進も育て始め
何もかも、どんな事態でも乗り越えられるというような状況に五代は喜び、六代も
そんな五代のお陰だと師を労う、そのやりとり、微笑ましかった。
そこへ縁側から一団が。
「ん~いい匂いがするなぁ」
「ホントだ、食欲沸くなぁ」
「あらあら…私もお手伝いしなくては、これからどんどん増えるのですし」
「あ、ではわたくしも…」
「いえいえ、お沙智さんは既に盛り上がっている二人とお倫さんやお宵さんを頼みますよ」
六代弥生が下座から
「あ、お宵さん! つい最近貴女からも出来る限り受け継いだ、
貴女が予言したとおりに動いている、貴女のお陰でまた一つ為すべき事を継いだわ!」
座礼で迎えるところに五代も
「お沙智さんからあたしの時代は時代に翻弄されるって予言、まぁ既に明治だったから
肌で感じてとにかく技を磨くことに捧げて六代に継ぐことが出来た」
座礼で迎える。
宵はちょっと照れくさそうに
「いやいや、思いを巡らせた上の勘でしか過ぎなかったけど、当たってくれたようで
何よりさ、それだけで私が生きてた甲斐があったってモンだわ」
そこで六代弥生が
「まぁまだ全部がやって来たわけじゃあないけれど、お陰でかなり備えられてる」
「うん、それだけで充分だ」
「飲み物如何します? 酒も色々ありますけど、珈琲の記憶がない、如何です?」
「ん、お倫から話には聞いてた、でも流石に入手が難しくて飲んだことないのよね」
「匂いだけは嗅いだことある、いい匂いだった」
お倫が言うと弥生は珈琲だけは作れる、淹れに行きつつ、戻る時には裕子もいて
「珈琲と言えばこれもどうぞ」
砂糖やミルクと言った物や、クロワッサンを添える。
「おお…こりゃ贅沢なパンだな、バターたっぷり使ってる匂いだ」
喜んでクロワッサンと珈琲などを受け取り席に着き香りの良さと、苦くて濃くて
少し酸味のある豆を使って居ることで、宵もお倫もミルクや砂糖で調整する。
更にアイリッシュクリームでアルコールも足す。
「うはー、うめぇ、もう死んでるけど生きてて良かったーと思うね!」
お倫がしみじみ言うとお沙智さんも微笑みつつ炭酸抜きをしていないどぶろくを求めたので
六代が注ぎつつ
「お沙智さんは冒険はしないので?」
「ええ、まず慣れたモノから…w」
「その割には結構渋い趣味をお持ちでw」
「うふふ」
と、そして本殿側からまた急ぐ足音と声がして
「先生! そんなに急いではしたないです!」
「ああ、でもこの匂い、私にはもう我慢出来ません!」
そして宴会場に入る二人、四代、五代、六代が軽く礼をしつつ、六代弥生が
「どうぞ、今この場でだけは存分に楽しんでいってください」
散り際の最も壮絶な二人に対する労いで、特に直の次代宵も頷く、そこへ千代が
「えー…でも、私も何かお手伝いしますよ」
そこへ出来た料理を運びつつお越さんがやって来て
「もう炊事場も一杯ですよ、これ以上多くなっても埒があきません」
葵もやって来ていて
「それに、千代さんって弥生さんの初恋の人にも似てるから! お話しして居てよ!」
「ちょ…葵クン!」
いきなりの図星に六代弥生が顔を思わず赤らめると、そんな風に言われると千代も赤らむ。
八千代が割って入って
「千代さんはあげませんよ? ええもう何があってもあげませんよ? あげませんよ?」
六代弥生は恐縮しつつ
「大丈夫です大丈夫です、もう、いや、似てることは否定しませんけど…大丈夫です
幾ら乱れていたって、そこの分別は出来ます、ええ、出来ます」
八千代は席に着きつつ、
「まぁ、富士さんに対する貴女を見ていれば信用も出来ますが…千代さんは
もう「知ってしまっている」わけですからぁ…」
六代も
「ええ、取り敢えず如何です、スパークリングワインなど」
酒を勧められると八千代も気が逸れて
「美味しい! これなら甘すぎませんから食事とも行けますね!
ああ、どれもこれも美味しそうです!」
と言って本当に満足そうに食事を始める。
千代は困りつつも六代に頭を下げた。
五代弥生の頃には海外の素材・食料や料理も入っては来ていたが
それらが大正・昭和を経て「和式洋食」となると五代も結構がっついていた。
調理も終盤になってきた頃、本殿のほうから
「あれ、なんと食をそそる香りでしょう!」
「相変わらずだね、弓」
二代と守が現れた。
出来た料理を次々運ぶ炊事組でも葵がキラッキラで
「守さん! 守さんにもボクすっごく会いたかった!」
守は葵をナデナデしながら
「うん、和の外れの支流で見てたよ、可愛いなぁ、葵って」
葵は顔を紅潮させ撫でられるに任せる。
「三代以降六代まで、お初にお目に掛かります、皆様それぞれに
力を振り絞り存分に生きていらしたこと、感じておりました、弓に御座います」
座礼で宴会組に言うと、三代から六代まで座礼で答え、まず八千代が
「貴女様の境遇からとは言え、授かった目の詞、わたくしにとっても大きな力になりました」
四代宵も
「必要ないかと思いつつ、右目をやってしまってからは私もその世界の大変さに
慣れるまで物凄く時間が掛かった、さぞ大変だったと思います」
五代は
「あたしは詞として知っては居たが六代に伝える前に…伝える段階飛び越す戦いで
一旦途切れさせてしまった、申し訳ない」
そして六代弥生
「あんなのがいきなり現れて中級だった当時の私じゃあしょうがない、それでも私は
今、貴女の記憶からそれを継いだ、お陰で成せた戦いも…あ、見ます?」
用意良く既に持ち込んでいたモニタとPCを繋ぎ、魔界都市新宿での戦いを用意するも
弓は顔を赤らめ、
「あの…申し訳在りません、まず…その…見たことのない美味しそうなその料理を…」
流石歴代でも随一の食べることが大好きな二代である、全員顔をほころばせ、守が
「悪いんだけど、弓が食べたそうな物幾つか貰っていい?」
裕子がそれに
「どうぞどうぞ、まだまだ作り増しも出来ます、物凄い買い込み量でしたので」
弓の目の前に見たこともない料理が並ぶ、弓は目を輝かせそれらを頬張って行く。
その至福の姿、見ている方まで幸せになる。
幾らか食が進んで弓ははっと気づき周囲の注目を集めている状況に顔を赤らめつつ
「い…如何なされました?」
お越さんが顔をほころばせ
「お宵さんも大概物好きで色んな料理を作りましたが、
そんな風に美味しそうに食べてくれることが幸せでしたよ、増して
貴女様のその本当に、動作から表情から全て、これほど美味しそうに
食事をする方がいらっしゃるなんて、見ているこちらも本当に幸せになります」
弓は顔を真っ赤にしつつ
「でも、これらの初めて食す物、本当に美味しゅう御座います」
そこへ六代弥生がにっこりして
「作ってない私が言うのも何ですが、存分に食べてください、
あ、お酒はあまり得意ではないようですが、この苺にごりの酒、美味しいですよ」
と言って小さなコップに少し注ぎ飲んで貰うと、それも矢張り「凄く美味しい」
という表情をする、それだけで、幸せになれる。
「弓にはやっぱりこうやってゆっくりしていて欲しい」
守が心からそれを言うと皆が頷く。
八千代がそこへ
「…まぁ…現六代以外は皆それぞれに、それがどう言う形であろうと
それぞれに終わったのですから、たまにはゆっくりさせて頂きましょう」
そこへ五代弥生も
「そうだね、まぁあたしなんかつい最近って言う感じだけど、それでもその時
六代はまだ小娘だったんだって思うと、時の流れを感じる」
応永、天文から永禄、明和から天明、そして明治、それぞれの時代を思いつつ、
また和やかな宴に戻って少し。
縁側で気配が一つ、そして
「やぁ、済まない、遅くなってしまった」
その声を聞き姿を認めた瞬間、全員が縁側に向け一斉に深く深く座礼をした。
面食らった人物は少しはにかみつつも「しょうがないな」という微笑みで
「おいおい…やめてくれ、私はそんな大したモノじゃない、むしろ後世に
重荷を押しつけた張本人とも言えるんだ、顔を上げてくれ」
代表して四代宵が
「何を仰有いましょう、あの時代、あのご時世、あの世情にあれだけのことを成され
我々のような「普通であれば次のない」者に継ぐモノと継いでゆくモノを
残してくださいました、貴女こそは偉大な初代に御座います」
最初に言を発したのが宵と言うことでお倫がその次に
「お宵と一緒になって刀も大分作った、でもやっぱりあれほどのモノはない」
そして六代弥生が側に居た稜威雌に
「さぁ、この場合貴女の居る場所はここじゃないよ」
稜威雌は六代のその確かな目に少しだけはにかんで頷いて、
そして八重の胸に飛び込んだ。
「お会いしとう御座在りました、八重様」
「ああ、まさかこんな時が来ようとは…巡り巡った縁というモノは本当に奥が深いな…」
六代弥生が続け
「では、上座へどうぞ」
「私が上座? そんな柄じゃあないんだが」
「何を言いましょう、貴女を置いて他に誰が上座に座るというのです」
二代から六代、そしてそれらの連れ合い達ほぼ全員がほぼ同時に一言一句違わず言った。
少し違ってたのは守とお倫と葵だが、言っている意味は同じだ。
八重は稜威雌を連れ立って少し居心地が悪そうに上座に着き周りの人々のススメで
色々飲み食いし、遠く流れ去った時間に根付いていった食べ物や酒の質に驚いた。
「今の清酒は本当に澄み切った切れ味だな、美味い」
鎌倉時代の清酒は一歩間違えると今で言うみりんに近いモノであった。
澄に澄み切った清酒に地味にあまり昔は食べることがなかった刺身を突いている。
その所作の一つ一つ、矢張り決まっている、無駄なく隙なく、そして味を噛みしめ
満足げに食べ進める。
千代がそこへ素朴な疑問で
「それにしましても、何の用事で「遅くなった」のです?」
稜威雌にも食べ物や飲み物を沢山勧めつつ八重が
「…うん、今頃、そろかな、と思って少し探したんだが、見当たらなかった
居たら呼ぶつもりだったんだが」
その言葉にピンときたのは六代で
「その巡りはまだ来ていないようです、修行は始めて居るにしてもまだ
「出会ってすら居ない」十歳ほどのようですよ」
「そうか、まだこれから…じゃあ結構先に為るのかも知れないんだな、
しかし私が彼らと出会ったのが数え十五とかそんな時だったから…では六代」
弥生はしっかりとした強い光の微笑みで
「判っておりますよ、今度こそは全てを巻き込んででも終わらせましょう
いつまでも引っ張っていられる事ではありません」
八重も目を伏せ口の端を上げ
「心強い、流石全てを受け継いだと言うだけはある、
「それ」が終わって私達は初めて本当に和の中に戻るのかも知れない」
しかしそれに六代弥生は
「さぁ、それについては、稜威雌が稜威雌である限り、また機会もあるかもしれません」
初代から五代まで、その連れ合い含め葵や裕子も「うん?」という空気を
「初代と四代の記憶のお陰で私はもう稜威雌をこれ以上細くすることもなく…
いえ、むしろ初代が初めて手にした時のような真新しさすら保つことが出来ます。
馴染みの刀工には「たまには稜威雌を見せてくれ」と言われてしまってますけど
その工場を借りる代わりに、私は既に稜威雌を祓いの力は材料の見極めのみで
当時そのままの姿を取り戻しましたよ」
そこへ宵が
「そうかぁ、正月の時の祝詞もすっかり受け継いだようだし、刀鍛冶の方も
初代と合わせて受け継いじゃったみたいだねぇ、玄蒼の地は仮令(たとい)死んで
和の端に戻ったとしても外からじゃ見えないんだ、勿論禍の国も
魔界ってヤツもね、だから表に見える所だけが頼りで」
五代弥生がビールを飲みつつ洋食を摘まみながら
「そういやそれで「見せたいモノがある」ってあんた言ってたよね?」
六代弥生が「ではでは」と既にセットし終わっていた大型のテレビとPCで
上映会を始める、それは魔界都市新宿での一戦だ。
◆
見終わった後、口火を切ったのは八重で
「後ですっかり治せる手段があってこその無茶苦茶さだな…そんなとこまで
私達に倣わなくても良かったのに」
二代から五代まで苦笑が漏れつつも、弓が
「しかし…時の流れも感じますね、皐月様も御奈加様も流石にお強い、
現代には現代の力の均衡が在りましょうが、これほどまでの激しい世界になっているとは」
宵が結構真剣に分析し
「いや、これ時代がどうのって言うか、奇跡的な巡り合わせと言える、
なるほどそりゃ、大きく魔界も動くってモノか、因果だねぇ」
八千代も加わり
「ええ、御奈加さん、とんでもなく頑丈です…流石四條院本家の相方と言いますか…」
弓に帰り
「詞の複数掛けも当たり前、あれほどの猛攻を一つも洩らさない守りの領域
確かに皐月様、随一の強さと言えます」
五代も
「あたしは本家には携わらなかったが、明治の世でもここまでのは居なかったと思う
弥生、これ一人で行けたか?」
「前提が幾つも必要になるかな、同じ装備でただ一人では無理」
そこへ初代が
「うん…まぁ無理だね、身の程もキチンと弁えてる、矢張り継げるモノは継いだ上で
六代の縁がこの流れを作っているんだろう、そう思うと危なっかしいが
その場に居たのが私だったらと思うと…(苦笑しながら)大差ない終わり方だっただろうなw」
そこへ守が
「八重様はでも祓いの目は知らなかったって事になるけど、
そこから祓いの四肢にまでしちゃった八千代さんはともかく、弓や八重様は」
ほんのり酔いの回った弓が幸せそうに苺の濁り酒を少し飲みつつ
「私の場合は…必死で編み出していたかも知れません、それこそ八千代さんが
そういう状況で編み出したように…」
なるほど、と思える。
「私か…実はこれは祓いの目と言えるのかは判らないんだが光じゃないモノの見方は
心得ていたんだ、空や石の発する僅かな…六代、そういうのはなんて言うのかな」
「放射線ですね、流石です、ほぼ祓いの目を独自で会得していた事になりますよ
貴女のことです、落ちてしまった四肢を「祓いでつなぎ止め治しながら」
「今ここ」という瞬間を狙っていたと思いますね」
「うん、そんな感じだろうな、流石に祓いの四肢までには届かなかっただろう
けど、何が在っても潜むだろう一点だけは絶対に狙ったと思う…
ただ、六代弥生、一つ言いたいんだ」
少しビクッとした六代弥生、初代は稜威雌を抱き寄せ
「…あまり稜威雌を泣かせるなよ?」
「は…はい、魂に刻みます…」
汗たっぷりで緊張して言う六代弥生に葵や裕子は少しおかしかった。
二代から五代は苦笑した、稜威雌をいきなり抱くなんて、伝承が途切れかけていたにせよ
確かに何と無謀な事だろう、そう思ったからだ。
「私でさえ手を出さなかったのにw」
宵がそう言うと、稜威雌もちょっと八重には申し訳なさそうに
「まぁ…その…でも矢張り持ち手ではありますし…宵様はあの時点で
誰よりも無茶でしたから…何しろ玄蒼という魔や禍の強い土地で祓いも
他の地より回復の悪い場所でしたから、随分と心配しましたよ」
黙々と皆の話を聞きながら食事とお酒を楽しんでいたお沙智さんが一言
「全く、どのお方も罪作りなのだけは変わりませんよ」
それについてはほぼどの世代の連れ合いも深く頷いた。
全員立つ瀬なく、小さくなる、八重でさえも。
空気を変えるべく六代弥生が「あー」とひと息入れてから
「お宵さんは判ったと思うけど、平塚ってヤツ…」
「ああ、面影あると思ったら、やっぱ二宮の子孫か、あと…狛江さんだっけ
そのおっかさんが山桜の子猫のウチの一匹だったとか、
ろくに名前も付けてやれなかったんだけど、二宮はなんて付けたのかなぁ」
「平塚が自分の細かい出生まで知っているとは思えないんで玄蒼の知り合いから
今度魔界都市越しに教えてやるつもりで居るんですけどね」
「ビックリするだろうな、それにしても六代の着流しは私の体型に凄く近いせいもあって
ちょっと私もビックリしたよ」
「私もですよ、お互い生まれた時代を交換しても似たような人生歩みそうで」
そこへお越さんが
「そこも矢張り血なのですねぇ」
照れ笑いに近く宵が
「まぁ…そこはその、ねぇ、誰も何も言い返せないでしょ」
弓が溜息をつきながら
「わたくしが明治や今この時代に生まれていたら、さぞかし乱れていただろうなと思います」
「あー…私も否定は出来ませんねぇ…」
八千代も同調した
「私は…どうだっただろうな、想像も付かない、学ぶことが沢山ありすぎて
逆に縁も何もなかったかもしれないな」
八重がしみじみ言うと、なるほど確かに初代だけはと思える。
裕子がそこへ
「矢張り皆様それぞれの時代に在ってそれぞれの境遇があってこそなのですよ」
「うん…そう思いたいな、裕子か…恐らく古代十条の血は今ここに居る刀使いよりは
お前か…弓に近い血だったと思うんだ、弓の場合は師が大太刀を教え込んだことも
あって稜威雌も持てる技量になったが…」
一堂に会する誰よりも歴史の古い八重の言葉に皆が「えっ」と思い、六代弥生が
「何か伝承のカケラがあったんですか?」
「いや…なにも…だが大太刀や野太刀こそ源平の辺りに出て来た…
私からすれば「新たな潮流」だったわけで…そう、弓が矢の先と後ろで
役割の違う祓いを使い分けたように、祓いの矢で
それは中遠距離からの天野の助けであったり四條院の補助であったり…
或いはその二家が集中出来るように他の軍勢を牽制し、
ときに矢で遠くの負傷者を癒やす役目も在ったのではないかなと思うんだ」
なるほど、と思う一同、そして流石初代は思慮も深かった。
「ただ、その力の「本当の意味」が何なのかはずっと謎だった、だからこそ
政情に合わせ伝承も失せて長いこと五里霧中にあったのだと思う、
六代の力の暴走に歯止めを掛け、「やってしまった事をなかった事にする」
という本義は、恐らく大昔から在っただろうが、命がけ、
何しろ物の理など誰も知らないような頃だったからね」
八重ももうすっかり洋酒に手を出し、見慣れぬ洋食を突きながら
「確かになかった事にする程度や具合は今でもまだ五里霧中だろう、
…だが、そう言う意味では「本来の十条の力」も今また目覚めようとしているのかも」
力強い言葉に裕子が感激した、そんな時に五代弥生が
「…そういやぁ…昭和の初期に本州から北海道にやって来た十条祓いが居たは居たんだ」
六代弥生がそれに
「そういや、なるように任せたと言ってたけれど」
「…あの子は戦う事その物に向いていなかった、優しすぎてね、
中級くらいまでは育てたんだが、時代の変遷のほうが大きかった事もあって…
早々に引退して…今なんて名前になったんだったか…当別と厚田の間くらい…」
「忍満別(しのまんべつ)市、昔は珍しくアイヌ語由来じゃなく「水都(みなと)」
と呼ばれた村だった所」
(注:架空の地名です、別のお話の舞台になります)
「ああ、そうだ、そこに土地と家買ってひたすらその土地を静かに静かに清めて
それでも心の平静を得る事が出来ずに…ある日消えちゃったんだ」
「蒸発とかでなく?」
「いやもう、ホントいきなり存在がなくなったの、まるでどこか別の世界にでも
ふらっと行ってしまったかのように
…何て言うか、ホント静かな…後悔も怨念も何も「なかった」世界に憧れててね」
五代と六代のやりとりを聞きながら宵が
「…玄蒼なら騒ぎになるはずだし魔界も禍の国も有り得ないな、何処に行ったんだろう?」
五代に帰って
「判らない、でも、きっとそこに求める平静があったからそこに行ったんだと理解してる」
それはそれで残念な話だな、と言う流れで少ししんみりしつつ宴は続く。
「今この現代に発展し続ける医療に身を捧げ、その上で祓いに転化する…
きっと、裕子さんは確かに究極の癒やし手となるでしょうねぇ」
医者でもあった八千代が癖と共にしみじみ言うと、裕子も移ってしまった癖で心底溜息をつき
「やっとその第一関門を突破致しました…でもわたくし、ここから更に六年を医学に
費やさなければそれも無意味になってしまう、多大な学費も掛かります、
使える制度は最大限利用しますが、それもそこから先の将来も見据えなければなりません」
千代がそこへ
「やれますよ、弥生様に甘えていいのだと思います、先ずは修めるモノを修めませんと」
六代弥生は矢張りあやめのようなその物言いの千代に少し締まりなく苦笑し
「任せて、裕子の目覚めはひょっとしたら全国の十条祓いをもう一度目覚めさせる
切っ掛けになるかもしれないから」
「はい!」
八重がしみじみと
「そう、本来野太刀ぶん回してボロボロになってでも勝ちを掴む一匹狼なんかじゃ
なかった筈なんだ、それはあまりに呆気なくとも三位一体で盤石な大和の守り
だった筈なんだ、楽勝で終わってくれるならそれに越した事はないからな」
稜威雌持ちは、それこそ「異端」だったのだと八重は言っていた。
宵がそれに応えつつ洋食を頬張りながら
「それでも、きっと駆け引きと戦いに特化した血もあったんだと思いますよ、
でなければ鎌倉のあの時代から今この現代まで六人も継ぐはずもない」
「そうだな…そうあってくれるといいな」
少ししみじみしつつ、宴は続く。
第一幕 閉
戻る 第二幕へ進む。