CASE:Sixteen
第三幕
「鈴谷様が女でもあって子を産めるかも知れない、か、あの人にとっては
天地のひっくり返る事だったろうね」
次の仕事は急ぐ物では無い、武士の霊などがあっても、野生動物に襲われても
もう滅多な事では大丈夫という自信も付いた三人がその日の野営場所を決め
焚いた火を囲みながら罔象が熟々と言った、それに続くように桜が八千代へ
「祓いの眼ってそのような事まで詳らかにしてしまうのですね」
「光一つとっても細かく見る見ないを選べまして…
ちょっと細かな説明は難しいですね…物凄く鋭い棘のような光があるのですが
それで見ると体の中が見えてしまうのです」
「へぇ、世の中にゃ不思議がまだまだ沢山あるんだな」
「はい、私もそう思いました、でもまだそれを掘り下げる世の中にない事も判りました
だから難しい、それを続けて使い、必要な画だけを選んで要らない光を受け取らない
などというのはもう一つの技ですよ」
「そうか…弓様と稜威雌は聞いては居たんだ、でも、そういう方だったんだな。
当時交流のあった力って祖先からの伝えがあってね」
「四條院はその後当主にまでなった摂津様、これも四條院では語り草です。
そういえば摂津様も形は女で男性という方だったそうですが、
摂津様も鈴谷様のような両方併せ持った方だったのでしょうかねぇ」
「そうであるなら弓様が仰ったと思いますよ、摂津様は恐らく本当に「そういう方」であったと」
「なるほど、そうですねぇ…」
なんとなく場に「す」が出来て、そして罔象がぽつりと
「あたしらは罰当たりな三人だよ、でも、それでもいいよね」
三人が俯いた、三人して健康なのに同性愛者であるなど、そうなのかもしれない。
でも、そうなのだから仕方ない。
桜が書状を改めて広げしみじみと
「わたくし達三人の初仕事は…その三家三人が終(つい)ぞ良い時に揃う事が出来ず
検める事の出来なかった貴人(あてびと)の墓を三人で調べる事…何か凄く巡り合わせを感じます」
「天野は力様の代わりに私、罔象が」
「四條院からは摂津様の代わりにわたくし桜が」
「十条からは弓様に代わって私八千代が…巡り合わせですね…素敵です」
またうっとりして左手を頬に当てため息をつく八千代、何かこれが癖のようなモノだった。
その日は流石に燃え上がる事も無くいい空気で夜を明かした。
◆
そしてその地に到達した。
小高い丘の上に小さな神社と簡素な家が二軒、その鳥居の前には既に出迎えも居た。
「ようこそ、貴人丘杜(あてびとのおかもり)の管理と地域の祓いをしています
四條院 茶戸(さと)と申します」
地域はほぼ平定している事もあり、そこは四條院でも引退した者が管理していた。
引退と言っても祓い自体は出来る。
茶戸は六十は越えているだろう人で、とても穏やかな相をした女性であった。
「この土地に再び三家が揃うなんて、祖父や祖母も喜ぶ事でしょう」
そう言って一人一人に挨拶をする。
そして桜が気付く
「…と言う事は弓様の指南役四條院芹生様と芹生様の妻となった天野稚日女様の…?」
「はい、孫に御座います」
また一つ巡り合わせを感じた三人。
「と言っても…私がホンの小さな頃に亡くなったので良くは覚えてないんですけどね。
弓様由来の方で守様の方は良く覚えているんですけれど」
その時だった、「守」という名を聞いた八千代に電流が走ったように硬直し、そして丘の上を見
そこに一本の桜…満開のそれを見つけると走り出す。
きっちり鳥居の一歩手前で礼はするモノの何かに取り憑かれたように八千代は走った。
「八千代?」
罔象や桜がきょとんと見送りながらも不思議そうに顔を見合わせ、また八千代を見守る。
八千代はその桜の前に立ち、見上げると崩れるようにその幹に抱きつき、膝を崩し
すがるような姿になって行く、その右腕は祓いの腕になっていた。
片手で生きる事を辞さないと言っていた八千代が両手で抱きつくなんて。
茶戸がその様子を遠い目で見つめながら
「何か感じたモノがあるのでしょう、そこにはもう魂も何もありませぬのに
祓いの力とかでは無い本当に何か絆のようなモノがあるのでしょうね、
あの桜の裏を良く見てください」
二人がその八重桜と抱きつく八千代の奥に墓標を認めた、桜が思わず
「あれって…「まさか」…」
「はい、あの桜の下には弓様の骸、守様の骸があります
守様は私が独り立ちをする手前まで生きておりまして、亡くなって弓様の隣に
埋められたその時には見送りました、標(しるべ)が裏にある訳は…日当たりを悪くしてはいけない
という弓様の意志を守様が「感じた」と言う事に由来しておりまして、因んで二人とも…」
「と言う事は死に別れて四十年以上はここで過ごされた事になりますね」
「そのようです、でもいつも悲しみは前に出す方ではありませんでした。
いつも元気で明るくて、生きる術を何でも知っていて…私もそれでこのような
何も無いところで一人生きて行けるほどには術を学びましたよ」
守については余り詳しい伝えが無い事から弓の片身としてその亡き後
四十年以上をここで過ごしたという事を今知り、決して暗い物では無かったが悲しみを感じた。
そして鳥居の前の三人もそこに参じた。
八千代は泣いていた。
そして、ふっとその頭を上げ桜を見上げたその時、ざっ、と桜がざわめいた。
八千代はそれを目で追うようにして立ち上がり、そしてもうそれっきり、静かな空間に戻った。
「…何があったんだ? 八千代」
罔象が慎重に聞くと八千代は
「…判りません、自分でも判りません、でも、とても悲しくて、でもとても愛おしくて堪らなくなり…」
「二人があなた様に何かを托されたのでしょう、霊とか魂とかでは無い「何か」」
茶戸が静かに言う。
「まだ体ばかりはふくれた小娘にはその深い意味は詳細に判りません…
でも…何かを托された…そうなのかもしれません…、ああ、皆様申し訳ありません、
貴人のお墓…検めましょうか」
気を取り直しさて、仕事の本分…と言う空気になりかけた時に桜の裏から声がした。
「ここにオオキミの血筋など居らぬよ」
自分より少々若いくらいの少女のようなでも妙に威厳を感じる声だった、八千代は
「え…気付きませんでした、申し訳ありません、今のお言葉の意味は…」
「言葉の通りじゃ、ここにお主らが検めねばならぬほどのモノは隠れて居らぬと言って居る」
桜や罔象が茶戸に「誰ですか?」という表情をするも、茶戸も知らないようだった。
四人がそろっと桜の裏手に回ると、その人は巫女の姿で桜にもたれ座り、桜を見上げていた、
見上げていたのだが「見上げている」と言う事は伝わる物の、その目は伏せられていた。
「あの…どち…いえ、私は十条八千代、こちらが天野罔象、こちらが四條院桜…
百年以上前にここを検めようとした先人の宿題を今果たしに参じたのですが」
「敢えて礼を失する、名乗らんぞ、わらわは」
そして四人の誰も彼女を見た事・会った事は無かった。
八千代は当時の書状から書き起こされた図…桜が持つそれを見てから今現在の参道を見て
「しかしながらあなた様は実際に掘り検めた訳でも無いのにその答えを知っているようです
「なぜ」答えを知っているのか、「どうして」私達を止めるのか、
それを知りませんと私どももただ引き下がる訳にも参りません」
その言葉に罔象も桜も、茶戸でさえも頷いた。
「名乗らぬぞ、詳しい事など何も「知らぬ」ぞ」
八千代はその何とも威厳たっぷりな人の傍らに片膝を付き
「道理などは関係ない、祓いの世界を知る前の私ならそのような言葉には納得しなかったでしょう
祓いを知り、人の心に触れ交わり、そして今…祓いだとか血だとかそんな物では無い「何か」を
受け継ぎました…いえ、受け継いだような気がする、と言った方が正解でしょう
私はその答えを求め一生を使っても足りないのかも知れない。
でもそれでも私はそれを受け止め知らねばならないのです、未だ知らぬ明日のために」
そして続けた
「ですから、貴女様も何かをお持ちなら、出来れば伝えてくださればと思います
どうしても今はダメだというのなら待ちますよ、明日など無いかも知れませんが
私達三人の奥に息づく「何か」はいつまでも待ち続けます」
「…しつこいのぅ、お主らは本当に」
「だってそうしませんと先へ進めませんもの、そういうモノとなってしまいましたから」
「まこと厄介じゃよ、ホンのその時の手向けのつもりであった事が尾ヒレ足ヒレついて
いつの間にやらこんな世代やら何やらを紡ぐようなモノになっておる」
「はい、判りました、あなた様がフィミカ様ですね、お初にお目に掛かります」
八千代は敢えてそのままの姿勢で頭だけを下げた。
他の三人は矢張りすっ飛ぶ勢いでひれ伏してしまう。
「厭な奴じゃなぁ…じゃから名のらんかったのに」
「はい、なので、本来であれば平伏したいところを耐えておりますよ」
「むぅ…ダメじゃ、お主と根比べをしたところで負けは見えておるな判った、好きにせ」
八千代は片膝のままもう一つ頭を綺麗に下げて微笑み、そして平伏す三人に向かって
「許可が下りましたよ♪」
◇
罔象が「いいのかなぁ」という表情をしつつもしかしこちらも「初仕事」という晴れ舞台を
抜く訳にも行かぬと結局は敷石を剥いで脇に置き、穴を掘り、そして石室の扉までたどり着く。
「凄い…僅かな隙間すら詞で石を溶かし埋めたようですね」
桜がその入り口の石扉をまじまじと眺め感嘆の声を上げる。
「僅かな隙間も許さないほどカラビトの魂が隙を伺っていたようですね」
書状を横から八千代が見つつ、当時ここがどれだけ穢れの危機にあったかを思い起こす。
「カラビト茸か…そこにあるだけで人を惑わし狂わせる…そんな物がこの世にあるなんて」
罔象が言い伝えなどから思い起こし石の扉に少しずつ隙間を作っていった。
「滅多にそこまでにはならない、と言うのだけが救い…本当に、この日ノ本には異質も異質、
「あってはならない」不浄の塊…よくぞ祓われたと思います」
桜も詞で再び石を部分的に溶かし隙間を作っていっている、かわって書状をもった八千代が
「そしてその祓いをした十条が弓様でその所有がこの稜威雌様ですか。
…正直私などでいいのかなぁ…と思ってしまいますよ、重圧もあります」
「あるだろう、八千代、でもその刀はお前のモノだ、お前以外に居ない。
そればかりはあたしにも良く判る」
罔象の言葉に弓は腰元の稜威雌を優しく撫でるようにして
「…まぁ私には私の使い方や努め方がある…全く同じという訳には参りませんが
せいぜい先代先々代の名を汚さぬようにとだけは気を引き締めましょう」
そこへ桜が言葉による溶接を解き、罔象へ石の扉をどかす役目を代わって貰いつつ
「出来ますよ、貴女なら…初めてお目にかかった日、貴女は
そのまま放置でもいつかは昇華する霊に贐(はなむけ)として本を読み聞かせ
判らない字は教わり、そして昇華へ導きました、優しい心をお持ちです
野太刀・稜威雌も大変な名刀とは言え優しい刀とも言われて居ります、歴代もそうでしょう
今この時、貴女以外に所有者などあり得ない、そう思います」
「君津 青堀様、教わった時と言葉はホンの少しで御座いましたが
私にとって二人目の教師で恩師、死してなお本を読みたいなどと強い思いを残されるなんて
浮かばれなくなる事は望ましくは決して無いのではありますが、でもそれもまた「いとをかし」」
八千代が左手を頬に当てうっとりとため息をつく。
「流石に祓いじゃそれは許されない、気をつけなよ、八千代は」
「はい…努めます」
扉も開けられ、罔象・八千代・桜の順で中に分け入る。
既に丘自体への封は施してあって、弓の時代には狂ったように突入しようとしたカラビトの不浄も
今は無し、春の暖かい空気さえもひんやりとさせる石の通路を三人は進む。
「…この石棺が鍵になっているようですね、弓様によると三家揃って力を合わせ
祓いの光を白にするとか…」
桜の呟きに八千代が何気なく
「フィミカ様の祓いが白だそうですから、いらっしゃるならやって貰うのも手ですよね」
罔象が思わずそれに
「お願いしに行くのだけはやめて! あたしも桜も茶戸様もポックリ逝きそうだから!」
桜も力一杯頷いている、八千代が少々首をかしげ半ば申し訳なさそうに
「これも伝承の差なんでしょうかねぇ、私はどうにも今ひとつ畏れが足りないというか」
「フィミカ様がそれをお求めになっていない、と言うことはよく知っているんだ、
知っているんだけど…千何百年「それだけは」と伝えられたことだから天野や四條院には
無理な話なんだよ…八千代が個人的に交流を深める分にはいいと思うけどさ」
「敬う気持ちはありますし、畏れ多いと判ってはいるのですけどねぇ…まぁその、
冗談は置いておいて、では解錠と参りましょう」
「厭な冗談だなぁ、おい」
気を取り直し、祓いの気を込め三人が手をかざす、八千代もこう言う時は「右手の祓いの手」を使った。
すると石棺に反応があり、罔象がそれを大きく動かした。
恐らく「そうしないと動かないようにした」のであろう、そういう鍵だったのだ。
そして石棺のあった部分には手掘りで手で埋めたと思われるそれほど大きくない穴が。
三人とも意外な展開に思わず揃って穴近くに顔を近づけきょとんとするも
「…といって…検めない訳にも行きませんし…」
八千代が祓いの手をその穴の上にかざし、目を伏せた。
「…あれっ?」
見守る二人に不安が募り桜が思わず
「…何か不都合が?」
「えーと…なんと言いますか…これは…」
と、そこへ
「ほむ、掘らずに検めたか、お主の手…目の代わりに手としたか」
いつの間にかそこへフィミカ様がやって来ていた。
またもやすっ飛ぶ勢いになりつつある二人へフィミカ様が
「ええい、背筋を伸ばせーい!」
言われると体が反応して直立になろうとするも、そこの天井は低い、二人は頭をぶつけ痛がる。
八千代が思わず笑ってしまった。
「フィミカ様…w あの、こちらにお隠れになっているのは…」
「うむ、掘られるのは少し戸惑われたので答えを言ってやる、そこな骸はわらわの猫じゃ」
痛がりつつも罔象が
「猫!?」
「猫じゃよ、八千代とか申したか、お主なら判るな?」
「はい…犬とも少し違う…猫のようです」
「こやつは…呉の国であったか…船でやって来たらしい、
気付けば住処に居ってな、わらわがナニモノであろうと此奴には関係がない。
飯が欲しければくれとねだりに来るし、構われたければ祀りの最中じゃろうと関係ない
いたく気に入ってな、共に過ごしたが、犬より若干長生きな程度…ここに来た時に還り居ってな
ここで還ったのも何かの縁であろうとここに弔ったのじゃ、きわめて簡素に」
「…なるほど、そこへ当時の三家の祖先となるお方達が厳重な墳墓と「してしまった」訳ですね」
「…まぁ良いかと思ったが、再び目覚めることになってふと思い出して来てみたらどうじゃ
いつの間にか墓守の家系がおるわ弓は居るわ…四條院ではいつの間にか大事になって居るわ…」
流石に三人とも少々申し訳なく思ってしまった。
「…まぁ、わらわがかつてクニを統べるオオキミ…キミメであった事は確かじゃ、
ある程度はと思うたが、流石にのぅ…まぁお主らがそれぞれ三家のあるじであるというならともかく
お主らもまた手足である訳じゃから、検めぬ訳にもゆかぬじゃろう、難儀じゃと思う
おぬしらには同情するが、しかし判ったであろう、「こんなモノ」なんじゃよ、実際は」
そこで八千代が
「いえいえいえ、なんであれ情を傾けた大切な…ある意味伴侶ではありませんか」
「まぁ…そうじゃな、それでこんな事にまでなってしもうたのじゃから…
うむ、ここはもう良い、もう「ねこ」も充分じゃろう、これだけ手厚くされては
かえって逝けぬかも知れぬ、今すぐ解散とは言わぬ、しかし…少しずつここは野に帰してやれ」
「名は「ねこ」なのですか?」
「よく寝る奴じゃったでな」
「あら、ひょっとしたらフィミカ様の子が「猫」の語源かも知れないのですね」
「それはないじゃろ、もっと昔からちらほらと船に乗ってやって来ては人に飼われ
一生を過ごしもしたのじゃろうから、十人に七人くらいは「ねこ」と名付けたのではないかや?」
桜がそこへやっと口を開き
「積もり積もって種の名として「ねこ」となってしまった…」
「そんなもんじゃろ、そういうモノじゃよ、そうそう御大層な由来などそうそうない」
「そうかも知れませんね…」
罔象も思わず言った。
「と言う訳でな、わらわが言うのじゃ、もうここは野に還してやって欲しい
先ほども言うたが今すぐとは言わん、少し時を重ねても、いつか野に還してやってくれ」
三人顔を見合わせ、頷くしかなかった。
◇
その日はそこでまた一日を過ごし、書状に結果を認めフィミカ様の意向を伝えると言うために
その署名まで貰い、フィミカ様だけはまたふらっとどこかへ旅立って行ってしまった。
こちらとしては仕事の仕舞いがあるので同行するとも言えなかった。
出来れば同行したかった、畏れ多い人だからではない、彼女がとても寂しそうに見えたからだ。
いつかは神社を含め丘をただの野に還す、その事について矢張り茶戸にも生きる道がある訳だし、
既に引退を迎える祓いの手向け場所となってしまった節もあるので矢張り直ぐとは行かない。
時というモノは、例えどんな権威や力を持ったモノであろうと如何ともし難い流れなのだなと
全員でしみじみ思った。
◆
真相を知ってしまえばそんな物、報告に三人で上がった四條院本家でもやはり「騒ぎすぎた」
と言うことを少し身に染みさせた。
とはいえ、長年の懸案が一つ晴れたことは事実、あの土地を徐々に収束に向かわせる事を確認し
治療を始めた鈴谷とも僅かながら再会しつつ奈良を去ることになる。
弓や守も「その役目を終える」事を知っていて八千代に別れを告げたのかも知れない。
少なくとも八千代はそう思うことにした。
◇
郷里を発って幾日、ホンの幾日であるにもかかわらず、何かが大きく変わったような、
いや、実際に変わった部分もあるのだけれど、見えず実感も出来ないけれど何かが変わって行くような
何かそんな物を胸に三人が家の近くに戻ってきた頃
「あね様!」
八千代の表情が少し微妙なモノだったのがいつものほんわかと優しいモノになり
「頼(より)、ただ今戻りましたよ」
まだ十を少し越えたばかりの頼は子供らしい無邪気さで八千代に抱きつくと、八千代も抱き留める訳だが
頼は直ぐその異変に気付いた。
「あね様…右手が…」
「…ああ…、ホンの数日前のことなのに、すっかり頭の隅でした。
大丈夫ですよ、私の右腕は普段は見えないモノになっただけ、ほら」
祓いの手も使い、頼を「高い高い」する。
「ホンの少しの間でしたのに、また少し大きくなったような」
姉の右腕は光る何かになって自分を支えている、しかし高い高いであると高く上げた腕に
裾が下がる訳で、皮で塞がっているとは言うモノのまだ断面向こうの筋肉の衰えが無い事もあり
なんだかそれがとても生々しく感じられ、頼はビックリして
「あね様、痛いですか?」
「うん? もう大丈夫ですよ」
「では痛かったですか?」
「斬られた瞬間などはもう痛がる余裕などなかったです、
はたと気付いた時には痛かったのですが、痛みは抑える事も出来ます、もう大丈夫ですよ」
「お可哀想に、さすって差し上げたいのに」
「頼は優しい子です、それだけで充分です」
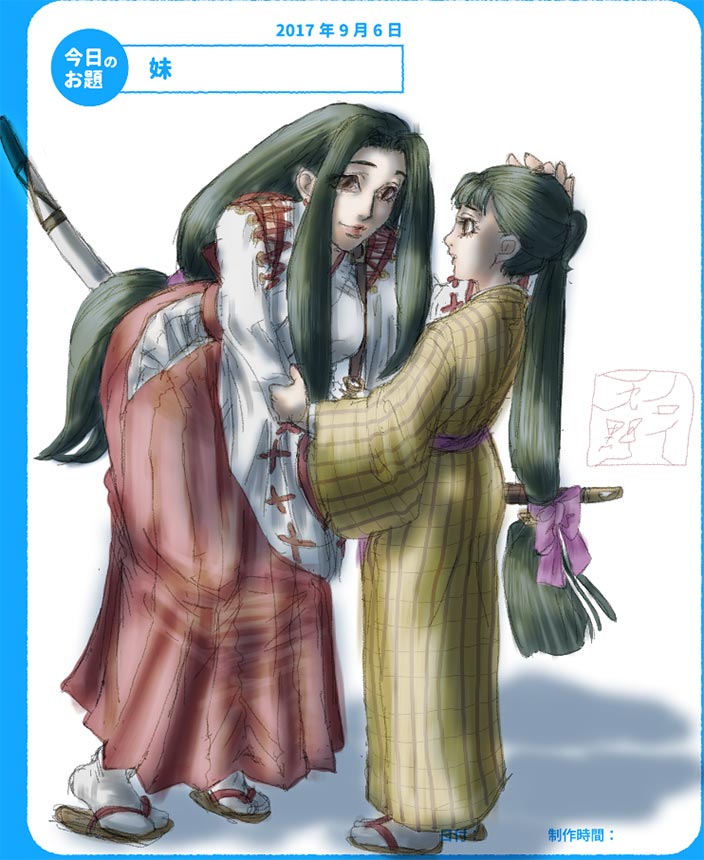
妹を地面に降ろした頃、弟(齢九つほど)も出てきて頼と同じように「あね様」とやってくるが
片腕になった姉を心配するよりは「何故そうなったか」「それでどうなったか」を聞きたがる。
そして、痛みに耐えられるかを聞いてくる、そして姉の授かった稜威雌、その頃には
常用は殆どされずに儀礼用、もしくは直して普通の太刀となったモノが殆どなのに残る野太刀に興奮した。
矢張り男の子だな、と一同は思った。
「んで、あね様! 土産があるんだ! 罔象姉(ねえ)も桜姉(ねえ)も!」
元気な弟、甲(こう)に引っ張られるように(実際、なんと八千代の右袖を引っ張って)
十条家に連れ帰ると、特に父の嘆きは酷かった。
祓いの腕という代価手段がある事を告げても矢張り我が子、父も母もすっかり悲しんでしまい
その時になってやっと八千代は「こんな事になって申し訳ないな」とも思ったが
飢えた母犬や母猫を通してその子達の命になった事、もしどうしてもとあれば
同じ年頃の女性の腕がもし手に入るならそれを接ぐ事も出来る事などを説き伏せやっと落ち着かせた。
罔象と桜はそんな八千代に「あたし達の気持ちが分かったかい?」という目線をおくっていた。
◇
「美味しい!」
八千代の顔が輝く。
「甲斐には舶来の葡萄が根付いて名物と成って居る事は知っておりましたが、
はは様はこれをお飲みになった事があったのですか?」
甲斐…現在のおおよそ山梨県は母の生誕地で、今回はその里帰りなどを兼ねた旅行であった。
「お酒は今回初めてですよ、いつもは実をそのまま食べてましたから」
「葡萄酒…素敵です、こんな美味しいモノが世の中にあるとは!」
余りの感激振りに先ほどの悲しみも吹っ飛び、和やかな雰囲気に包まれた。
罔象も桜も感激しているが流石にいい大人が「もっと飲みたい」などとは言い出せずに居れば
父巌や母笹子はそれに気づき、二人は八千代の姉のようなモノと気兼ねせずどうぞと勧める。
「帰って来た」そんな安堵が去来しつつ、しかし巌がこぼした。
「本当は樽で所望したかったんだが、近頃はどうにも物騒が濃くなってなぁ」
「何か危ない事態に?」
桜が思わず心配そうに聞くと
「いや、いい時期に旅に出られたと言われたモノでね…、確かに上から下から仏教から乱れて居るし
誰かが天下(てんが)を取らねば収まりもつかんだろうな、身分も崩壊しつつある、
祓いもその身の保証が難しいと向こうの祓いに聞いた、何とも、難しい時期に
娘達が巻き込まれる形になるのかと思うと正直引き留めたい気もする」
娘達、罔象や桜も含んでいるのだろう、二人は見つめ合いまぁそうかもな、とは思った。
そこへ八千代が
「あ、そうです、美濃の方で面白い湧き水がありましてね、中々に清浄であったモノですから…」
といって荷物の中から然程大きくは無いが壺を取り出し厳重に閉められた蓋を開ける。
「これと葡萄酒、合うと思うのですが」
それは今で言う炭酸泉の水、炭酸泉にも色々あるが、一行が道々見つけたそれは純粋な山からの湧き水に
地下の炭酸が溶け込んだモノらしく、雑味も何も無かった。
弟の甲が美味いを連呼し、目を輝かせる、その様子は矢張り八千代の弟、似た光だった。
頼も姉の腕をまだ心配しながらも美味い物は美味い、父も母も喜んだ。
「これは美味いが不味いな、子供が飲み過ぎてしまう」
巌の一言に既に酔いの回りつつある頼がクラクラしてきていた。
時代は油断のならないモノと成って居たが、せめてこの時ばかりはと和んだ。
◆
時は流れる。
十条の祓いが居ると言う事で割に大変なところへ三人で派遣される事も多く全国を回ったが、
それも三年ほどでもはや三人では多すぎる、と言う事でとうとう独り立ちへ向かって
八千代が一人で方々に回る事も増えてきた。
三人で愛し合う機会も減ってしまっていたが、その機会の一つ一つを大事にした。
そして天文二十二年(1553年)とうとう戦国の波は祓いに影響を及ぼしてきた。
二十歳(十八〜十九)となった八千代、流石に大人の風格にもなってきて
身の丈も五尺七寸にもなろうという長身、普段は片手だと言う事も気にならなくなってきた。
八千代はそろそろ独立も考えつつ主に東日本を回ったのだが、そのヒマヒマにたまたま実家へ
父の蔵書を読んだり写したりしに来ていた時である。
その頃にはこの地方に罔象や桜の弟子も居り、祓いの網の目で言えばしっかりと
結ばれた地域であったので割に初級や中級の手習い場所という認識にもなってきていた。
罔象や桜は祓いとして二人で地方を回りつつ…と言う事であったが、
八千代がたまたま寄った期間のもうそろそろ切り上げという日であった。
近所が騒然となり、人が大勢通りに出てきている喧噪が聞こえ、
しかもその言葉の端々に相手への気遣いの言葉がある、これは何かあったかと八千代も家族も
家を飛び出ると、多くの弟子や弟妹に囲まれた罔象と桜であった。
「どうしたんです!?」
八千代も思わず駆け寄る、囲んでいた天野や四條院の弟子達は退くが、その間からみる二人の様子。
ただ事では無かった。
罔象が口を開く
「やぁ、八千代…とりあえず…ウチの方へ…」
「いえ…その前に…足ですね?」
八千代は罔象の右足をに祓いの手で力を及ぼし始める。
「これは…鵺ですね…大変な祓いを…でもお二人ならこんな…何があったのです?」
「…霊は見えぬが魔は見える、これが行けなかった。
出先で鵺が暴れているのは任せてくれって言ったのにさ…武士と言っていいのか…
はっちゃけやがって…横入りで手柄立てようとめちゃくちゃでさ…
そいつら守りつつ…でもそいつらもう大局なんて見えてなくて…
もう後一押しって時に鵺の尾が足に噛みついて…まずい、と思った瞬間にはあいつら
無理矢理倒してとどめを刺そうとして…あたしらが下敷きになっちまった」
「治療がおくれてしまいましたか…これは…」
「あたしの足はもう戦いには使えないよ、祓いで何とか立てるってくらい…
もうボロボロなんだ…でもあたしはまだいい、桜なんだ八千代、桜の怪我…頭なんだが
何とかならないか」
すがるような罔象に八千代は胸が締め付けられた、そして一見ちゃんと治っているように見える桜は
八千代に向かって首を横に振る。
「…診せてください」
そして、頭の中まで検めて惨状を知った。
「下敷きになった時に…何か…武器片ですか…? 可成り深く…」
「そうなんだ…桜…言葉が出づらくなっちまって…体の方は大丈夫なのに
天野のあたしは足、四條院の桜が言葉を使えなくなっちまった…」
「…なんと言う事を…」
周りの弟子や親兄弟までも悲しみに包まれる。
八千代の父、巌が
「何とかならないのか八千代…」
「罔象さんはあるいは…でも毒で壊れてしまった筋と筋の繋がりは例え大きく
脚その物を入れ替えたとしても…復帰までに可成りの年数を…そして…
頭の傷は…難しいです、出来るだけはやります、いえ、やらせてください
いえ、やらねばなりません!
どうやら既に奈良で追加治療もなさったようですが…私も抗いに参加します!」
弟子達が自分の脚を頭をと言うがそんな事は無理という物、
悲しみの中桜の家の離れで大きな格闘が始まった。
父も書物やあらゆる人脈から知識や医者を募る構えだった。
…それらが徒労とまでは言わないが可成り厳しい物であった事は、八千代の人生初で味わった
挫折という物であっただろう。
第三幕 閉
戻る 第一幕へ 第二幕へ 第四幕へ。