CASE:Twenty
第十二幕
「…なるほど…体に取り込まれなければならない物の種の吸収が少々悪いな…
これを根源まで遡ると…この辺りを…」
京の四條院邸にて八重が寝込んでいる一人の少女の様子を見ていた。
倦怠感に包まれたその少女は細い体を八重に委ね、その治療を受けつつ
「わたくし…治るのでしょうか」
「少なくとも良くは為る、これは病だが生まれ持っての物に近い、
そこでだな…おい、淡女(うすめ)」
病床にはもう一人少女が座していて八重の言葉にそちらを向く。
どことなく表情の少ない、感情の余りない感じの少女。
同じ年頃と言う事でそれとなく少女の面倒を申しつけられている。
天野というのは大体その命をそのまま祓いに転化するのだが、
人として生きるための「何か」を犠牲にその力を具象する事もある。
この天野淡女はそういうタイプで、「欲求」という物が極端に乏しい。
「お前にこの子を任せたい」
「でも、どうすればいいのかさっぱり」
「詞を教える、いいかい」
そう言って「直ぐ治すからな」と少女の指先を少し切り、その血を小皿に少し。
そして荷物から何か標本のような物を取りだし、その一点を淡女に示しながら
自らの血も混ざらないように指先に滲ませ
「皿の上の沙緒理(さおり)と私の血を、その詞と共に良く見てみるんだ
眼で判らなければ触れない程度に指先でもいい…
その中に、これが私程度には含まれていなければならない」
淡女と呼ばれた少女は詞を覚え、唱えつつ、診たり触れない程度の指先で試すも
「…言われてみれくらいにしか見えないし感じない…埒があかないな」
淡女は皿の上の沙緒理の血を舐め取り、味わう。
そして僭越ながらと八重の指をまた舐める。
「…これか…確かに沙緒理には少ない、他の…この表のこれやこれも
少し足りないな、これが沙緒理だけの症状なのか」
舐めて舌で味わう事でそれは指先よりも何よりも正確に「物を見た」
八重は少々驚きつつも
「家全体で食べる物は調理法などが少し違うだけでみな同じ物を食している
嵯峨丸の体はくまなく見て回っているが、今まで診てきたどんな血と
比べても沙緒理だけは何かこう言った体に極少ないが必要な鉱石の吸収が弱い
それが巡り巡って体全体を上手く機能させていないようだ」
「待ってくれ…」
淡女は目をつぶり自分の体をなぞったりして頷きつつ、
沙緒理の体にも触れ、でも矢張り自分の体ではないと触っただけでは判らない
と言う事でその体をなめ回した。
沙緒理が真っ赤になって少し困るし、八重も苦笑する。
淡女にはこれが場合によっては「愛撫」に相当するなどと言う意識はまるで無いのだ。
実に平坦な精神でそれをやっているが、沙緒理にとってはくすぐったいを通り越して
少しその気にも誘われてしまう、だが、人前だ、沙緒理は我慢した。
八重は苦笑の面持ちで沙緒理の頭を撫でて
「淡女はなかなか大した物だぞ、血や汗、体から僅かに漏れる皮膚の欠片
そう言った物からお前の体の何もかもを今理解して行っている
お前に何が必要かを、その身で知っていって居る」
淡女が沙緒理の体から口を離し
「…なるほど…鉄…亜鉛…銅…他にも名前も知らないような鉱物…巡り巡って
人の体を上手く動かしている物なんだな、そして沙緒理はそこが上手くないと言う事も、
私はただ知っただけではダメだ、これらを如何すればいい」
「そうだな…ホンの少しだけ多めに与えつつ、
本来取り込まれなければならない場所に取り込まれる事を後押しする…
それで体が上手く機能するようになれば自然と沙緒理自身の体が
祓いの後押しもあってそれを覚えてゆくだろう」
「なるほど、承知した」
「こう言う物は大は小を兼ねない、与えすぎれば中毒を起こして死ぬ事すら在る
地道に毎日向き合わないとならない、大きく東と北日本を持ち場にする
私には出来ない、頼むぞ」
淡女は礼でそれに応え、沙緒理は少し心苦しそうに
「面倒を掛けて本当に申し訳御座在りません」
八重は腕組みをしつつ微笑んで
「誰もがお前の元気な姿を望んでいるよ、誰もお前の事をお荷物などと思っては居ない」
そこへ淡女も
「沙緒理、あんたの祓いの気は私に馴染みやすい、あんたが祓い人として
組んでくれた方が私はいい、賑やかすぎず、華やかすぎず、静かで
それでいて命の力に溢れている、命の力、私にはそれが足りない
生も死も渇望できない、しかしそれでは行けないと言う事だけは判る」
「外見は華やかなんだが、淡女にとってはどうでも良い事のようだな」
「沙緒理がどんな姿の何者だろうと構わないよ」
八重は俯いてフッと笑った、こんな熱い告白、早々聞けないだろう。
実際沙緒理はもうその淡女の言葉が染みついて響きまくっているようだ、
そしてその生命の波動とでも言うのか、生き抜こうという欲求が強くなったのを感じる。
「…それにしても、兄様が姉様になるなんて」
「戸惑いはあるだろう、狼に転身できる大丸と男から女に成り代わってしまった嵯峨丸
ぶっ飛んだ…だがしかしお似合いの二人だよ」
「それで…にい…姉様はいつお戻りになるのでしょう」
「ギリギリまで祓いの仕事は続けたいと言っていたからな…
そう…年越し辺りに戻って備えるのではないかな、
春になる頃にはここは忙しくなるぞ、それまでには動けるように、
そして祓いの修行を出来る限り積んでお呉れ」
沙緒理は体を起こし、淡女と共に頷いた。
◇
また八重は東日本北日本、時には蝦夷地まで赴いて仕事に奔走する。
何かが急な流れになって自分を流している、自分はその流れに乗りつつ、
自分の力で泳ぐ、その行く先は何処なのか、魂はどこから来てどこへ行くのか
生きとし生けるもの、いや、形ある物みな全て最後に向かえる物は
死、或いはその形を無くしその役目を終える事だ。
どんな物であろうと、それは変えられない。
医師でもある祓い、特に八重はその原因や細かい対処法などを知るだけに
普通の祓いなら呼ばれないような時にも呼ばれた。
死んでゆく者、生まれてくる者、生まれながらにして死んでいる事すら在る。
とかくこの世はある意味で分け隔て無く生と死が散りばめられている。
貧富で多少の差はありこそしても、基本的に生きる事は死ぬ事と背中合わせである。
そしてまた、身分や貧富ではなく部族…とでも言うのか、日本人以外と
関わる事も多くなっていた。
多くの場合それはアイヌ、そこから伝って女真族であるとか少数民族であるとか。
どこに居て、それが何者であろうと、その生と死を見てきた。
病気であるとか、怪我であるとか、理由は様々なれど。
八重は郷に入りては従えるだけ従う人物でも在ったので信頼はされた。
流石に入れ墨だの性的な風習だのは断ったが。
北国の短い夏を見て回っては密かに地形や気候、そこの生態も調べて
幕府にも朝廷にも献上した。
本格的な測量をして居るわけでは無いので朧気な部分はあるが、
とにかく日本国として蝦夷地は最終防衛ラインとして今は無理でも
いつかその勢力下に置くべき事など進言もした。
若い頃に抱いた疑問や知りたい事を一つ一つ、まだ哲学の範囲内では在るが
それらをただ経験則に頼るだけでなく、観測と実験に基づいて調べていった。
見た目が図体も大きく女なのに逞しいわ傷だらけだわ可成りワイルドなのに、
知性的で物静かな印象、そして我欲という物はほぼ見せなかった。
我欲を見せないのはただ見えないだけではあるのだが、
見る人には可成りの人格者にも映る。
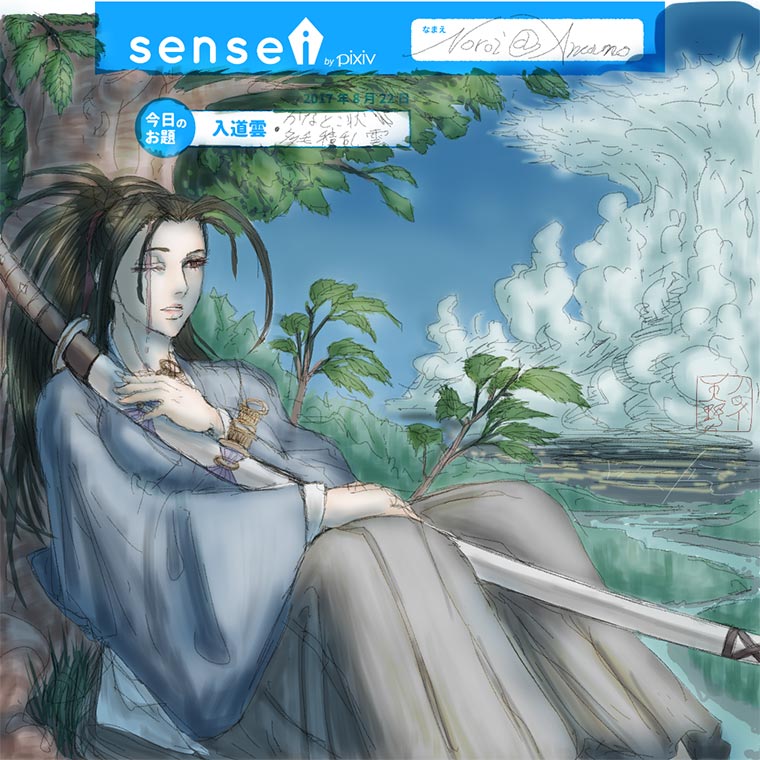
八重がまた夏の蝦夷にて仕事の途中、珍しく大雨が降った。
たまたま雨よけに良さそうなとても背の高い蕗が群生していたところがあったので
少しひと息つくついでに雨宿りでもしようかとそこへ行くと、
その人の背丈と優に超える蕗の群れの中に、蕗の葉で屋根を葺いた
竪穴式住居が紛れていた。
おっと、八重は驚かさないようにゆっくりその脇へ歩み寄り、
窓から鮭を燻し加工した物を中に捧げ、ややたどたどしいがアイヌ語で
「雨が上がるまで、ここの蕗をお借りしたい」
とだけ告げて腰掛けに良さそうな場所と蕗の屋根の下で着物をぱんっ、と
振ると、祓いで一気にそれが乾いて揮発してゆく。
蕗の家から老人の声が。
「おお…あなたは何のカムイでしょう」
「私はカムイではない、そうだな…カムイに仕える者に仕える…使いっ走りだよ」
「そうですか…貴女はきっとその命全うした時には良いカムイになるでしょう」
「それは…無理だなぁ、何のかんの、私はただの人だ…少しばかり
普通の人々より色々出来るだけの、ただの人だよ」
「命は巡ります、その巡りを一つ一つ積み重ねる事で、
いつかきっとカムイになれましょう」
「なるかな、私は死んだらどこへ行くのだろう、そしてまたどこかに
生まれ落ちる物なのだろうか」
「川の足(上流)にて生まれた魚は川の体で育ち、そして川の頭(下流)から
大きな水に旅立ちます、そして為すべき事を為して戻り、子になる」
「確かにそれは命の巡りだ…海に泳ぐ魚にも育つべき場所と巡るべき場所がある
何か…決められた何かがある」
「全ては生きてそれを全うするためです、そうしてカムイコタンに戻る、
その魂はそうしてまた何もかもを元に戻して再び生を全うする為に降りてきます」
「…水、今降ったこの雨は地に染み入りいつか岩を通り湧き出でて
その一滴一滴が沢になり、小川になり…それが集まり大河になり、
海へ注ぎ…そして海から空へ一粒より小さな水として登り、
雲になり、雨になり、そしてまた地に戻る…なるほど…
時に途中で渇くも、人を含めた生き物に飲まれるも、いつかはまた
体から出て天に戻る…全ては巡る、形を変え真っ新になって、また戻る…
有り難う、エカシ(長老)私は何か開くべき物に手を掛けた」
「水…、そうですか、なるほど、沸かした水は確かに登ってゆきますな」
「雲はそうした煙になった水の集まりさ」
「また一つ、世界を知った、でもそうすると知らなければ為らない事が増えます
この年ではそれはもう難しい話」
通り雨のようなその激しい雨も止んできて、空の向こうの雲が開け、日が差す
八重は晴れ晴れとした表情で
「そうでもありませんよ、蕗…幾つか貰ってゆきます」
八重は環頭太刀でこの辺りの植生に影響のない、そしてこの小さな蕗の下のコタンに
影響のない範囲で幾つか蕗を切り、見えない位置であろうと最敬礼でそこを去る。
◆
そして次の年になった。
嵯峨丸と大丸も嵯峨丸の実家に帰省し、大丸が単独で…そう広い範囲では無いが巡りつつ
梅が密かに彼らを守っていた。
この頃になると四條院本家筋や十条本家…詰まり八重の実家、そして朝廷にも
詳細は避けつつ三人で相談して梅という魔人の存在と、彼女は決して根っこでは
敵では無いと言う旨を伝えていて、嵯峨丸が子を産むまでという条件で
京周辺の往来も許可され、京周辺の祓いには通達が及んだ。
「済まないね、手間を掛けさせちまって」
梅は嵯峨丸の家(神社)には入れないのでその近くで休める場所に四人座って話していた。
嵯峨丸も大丸も梅の本当の正体まではまだ知らない。
祓いの世界を含め現世に大きな魔と祓いの巡り合わせがあるなどと言う事も。
それは八重が独断で誰にも伏せた。
「こっちこそ、済まねぇな、だが…流石に俺一人じゃどうにもならない」
今はまだ冬、腰は掛けていたが大丸は嵯峨丸を膝に載せ、寒くならないように
包み込むように大事に抱え、そしてその手は大きく膨らんだ腹を特に守っていた。
大丸も急激に大人になっていて、もはや青年と言っていい精悍さとたくましさ、
それに包まれた嵯峨丸ももうすっかり表情から何から女であった。
「私もいざその時にならないとこちらに張り付けないからな、
婆さんには悪いがしばらく厄介祓いを頼むよ」
八重も言う。
「それは構わないんだが一時とは言え祓い公認の魔人など前代未聞だねぇ」
「祖母という存在をよく知らない僕たちには、お婆さんは誠のお婆さんのように思います
厳しいけれど、僕らを導いてくれる師匠でもあるとさえ思っています」
「くすぐったい事を言うねぇ、イヤな気がしないところがイヤになる」
梅の苦笑に一同が和む。
「ホントなら生まれてくる子に名を付けて欲しい位なんだぜ、俺も嵯峨丸も異存ないし」
「それは勘弁してお呉れ、嵯峨丸のご両親かあんたらが付けなよ、あんたらの子だ」
嵯峨丸は自らに宿る命の居る自分の腹をさすりながら
「…どんな子が生まれるんだろう、次を托されるにしても、どうか幸せであって欲しい」
親としての本音、出来る事なら魔と祓いの戦争の駆け引きなんかに巻き込みたくはない
でも、それは自分たちが、そして魔王や神ですらはっきりとは決められない事。
「性別とどんな外見をしているかくらいなら判るけどな、それは
生まれてからのお楽しみのがいいだろ、私もそればかりは無粋をしたくない」
八重が言うと、梅がしみじみと語る。
「八重、あんたに出会えた事は何よりの幸運だった、
大丸嵯峨丸、そしてアタシってだけの構図なら、もっと危機も多かっただろ」
「でも私は何も本当に「ただの巡り合わせ」と言う訳でもないようだよ、
婆さんと初めて会う切っ掛けだったあの村に、私は大丸のような祓いに
他の例がないかを調べに行っていたんだ、絡まるべくして絡まった糸なのさ」
「そういえば八重様の元でと言う話は実際にそうなる二年ほど前にはありました」
「どんな人なんだろうと思ったら俺より男らしいというか頼もしい人だもんな
流石なんだけど、結構立場なかったぜ」
八重は目を伏せ含み笑いをして
「こっちが先に生まれてこっちが先に独り立ちした…それだけの事さ」
「そうは思えないんだよな、なんかこう…全てが一番良くは行かないとなって
そんな時に二番目をさっと見つけて整えてくれるようなそういう人だ。
時間は短かったけど、最大の師匠かも知れない」
大丸の言葉に嵯峨丸も頷いた。
「よしてくれ、私もイヤな気がしないところがイヤになる」
場が笑いに包まれる、こんな雰囲気ですんなり行ければいいのに、
本音では誰もがそう思った。
◇
「…うん、何処にも病の種はない、そして祓いを持っているようだ、
藤枝様、後は突然の事故などにお気をつけください」
藤枝の子…詰まり倫理的にはどうあれ義理の息子用宗(もちむね)との娘、
こちらも元服を迎え、物の分別や踏ん切りは付けられるようになっていて
娘に関しては「阿拝の血縁筋が震災によって被災した落とし子を阿拝が引き取った」
と言うカタチにして、それに納得していた。
「十条様にはわたくしも、母も大変お世話になりました、言葉にも尽くせぬ思いです」
元服間もない用宗だが、如何して立派な物だ、背負う物の重さを知って
その覚悟を決めた強い目であった。
「本当に、感謝してもしきれない…」
「その礼は…桜の盛りを少し過ぎた頃、京都に赴いて大丸と嵯峨丸に言ってください」
「そうだな…礼を言わないと…向こうも子が生まれるのであったか」
「ええ、順調です」
「であるなら…」
阿拝が小さな木札の表に何か印と共に詞を、そしてその裏に自分の、そして娘の
更に筆を用宗に渡し、その名を認めた。
そしてそれを小袋に入れ更に詞を込める。
「これを…あの二人、いや三人になるのか…に渡して欲しい」
「しかと承りましょう」
八重はそれを受け継ぎ、藤枝家の下働きのような事もするようになった
川向こうのまだ未熟な二家の数人が去る八重を見送った。
◇
そして京に桜が咲き始めた頃になった。
祓いの通達で「梅から」連絡があり八重は都へ跳んで帰った。
「いや…済まない、そうだよな、桜は南から北へ向かう物だった
受け持ちが北でいる事も多いからうっかりしていたよ」
「嵯峨丸は元気だがもう流石に動き回れない、詳しく見てやっておくれ
そしたらアンタも公にこちらへ張り付けるだろ」
「ああ、わかった…と、そう言えば今更思い出したが、キミメ様へは
伝えてくれたのかい?」
梅は少し渋い顔をして
「ああ、伝えたよ、今頃はもう各地の祓いやお内裏にも通達は回っているだろうさ、
勿論蓬莱殿にもね、それだけじゃない、墓守の家系にもさ。
アンタも策士だね、キミメ様の鶴の一声なら誰も疑問にも思えない」
「使えるモンは何でも使うのさ、例えそれがキミメ様でもね」
「畏れ多い奴だねぇ」
「…ま、咎があるなら受けるさ」
「そんなモンはないよ、鼻息荒くやる気になって居られたからね」
「話の分かる人だな、会ってみたいよ」
「どうかね、いつか逢えるのかもね」
「とりあえず嵯峨丸の様子をうかがおう」
梅が塀の上で見守る中、八重が嵯峨丸の容態を含め詳しく診てゆく。
そわそわした大丸が
「…どうだ?」
「順調だよ、うん、腹の中の子も元気だ、そうだな…二日三日後かな、この調子だと」
大丸はすっかり夫の、父親の顔になっていて労うように嵯峨丸の頭を撫でた。
西洋人の父も母も、妹の沙緒理も淡女もそこに居て、待ち遠しい思いと
その時にやって来るであろう危機とで安堵と不安の入り交じりになる。
「俺が守る、何があっても嵯峨丸も子も守る、ただ、八重さんも
父さんも母さんも、沙緒理ちゃんも、どうか、俺に力を貸してくれ」
しっかりと大丸が頭を下げた。
意に沿わないようなときにはちょっとぺこりとするくらいだった大丸が
この三年近くで本当に成長した物だ、八重は微笑んで
「当然だろう、沙緒理もだいぶ育ってきたな、体力に少々難はあるが、
越えて見せてくれ、淡女、しっかり沙緒理を支えてくれ」
二人も強い表情で頭を下げ返礼する。
「べぇるさん、この国に来て幾星霜、武具の鍛練は積んでいるだろうがあとで
腕前の程は見せていただく、海の向こうの更に向こうからやって来たという
げぇるの魂を見せてくれ」
嵯峨丸や沙緒理の父ベール、日本で日本名を授かり「流兵衛(りゅうべえ)」と
元の名をもじった物であったが、八重は一貫して元の名の「Beal(べーる)」で呼んでいた。
ベールも息子改め娘、その子、孫の危機である、強く頷く。
「紗代(さよ)さん、半ば引退の身で感じを掴むのにも一苦労だろうが宜しく頼む」
そして母の紗代も強く頷く、
改めて大丸と嵯峨丸が「どうか宜しく」と頭を下げる。
と言ったところで八重が
「今日はこれから大丸以外戦えそうな全員の腕前やら様子を見るが、明日一杯を私に呉れ」
その八重の言葉に一番反応したのは庭向こうの壁の上の梅だった
「何だって!?」
「私には私のけじめがある、どうか一日呉れ」
場が一気に重くなった。
勿論勝つために戦うのだが、或いは命と引き替え…
そう、勝利条件が嵯峨丸の無事な出産だというなら、自分が生きている必要は無い。
「如何したんだ、私は別に進んで死にに行くその前に言い残したいと言うわけじゃあない
ただ何があっても後悔はしたくない、それだけの事だ」
「…判ったよ、その間の守りとひよっこどもの面倒はアタシが見るさ」
「済まないな」
◇
「頭、ちょっと稜威雌の調子を見てくれないか、いや、刃に異常は無い
鞘、柄、鍔、その全てを最高の状態にしておきたくてね」
次の日、八重は京から刀工まで足を伸ばしていた。
頭は稜威雌を受け取りながら
「…寸法は判っていると言いたいが、これ以上無いほどの整えには確かに
刃もなくてはな…判った、何か大きな事があるんだな」
「ああ、墓参りしてくる」
「鞘や柄となると専門外だ、八重殿からの強い希望と伝えて同行しよう」
そして一女の墓に詞を捧げつつ祈る八重、
「八重殿」
詞を捧げ終わり、少し黙祷してから八重は振り向く事無く
「長いような、でもジジイとの付き合いからしたらあっという間の付き合いだったな」
「死ぬのか」
「それも算段に入れなくちゃ少なくとも勝ちに行けない」
「そうか…」
「だが、刀は残す、何があっても残す、十条の祓いの中でも、
きっとあの刀が必要になる者が現れる、私と一女が生み出した「継ぐモノ」だ」
「…判った、見た感じ調整などほぼ要らないようだったが、
それを聞かれないために預けたのか」
「婆さんにも言われたよ、罪な女だと」
「しかし人と刀、扱い方によってはどっちが先にもなり得る代物、
増してあの刀はもうただの刀ではない、八重殿の覚悟は良く判った。
迂闊な事は言わない、ただ、「勝って」くれ」
「ああ、それは必ず」
そこで八重は頭に振り向いて
「もう少し、稜威雌を預かっていて呉れ、如何しても会っておきたい人が居る」
「帰りには湯浴みもして行くといいよ」
「ああ、有り難う」
◇
「なんだいなんだい、「死ぬ事も覚悟した目」をして居るよ」
武蔵国、姐さんの花宿。
「やっぱり姐さんだな、そうなんだ、私は必ず勝つ、だが
「これっきりに為る」事だけは排除できないんだ」
姐さんは流石に少し思い詰めたような表情で、いつものように柱に背を凭れ
腕を組んで居たが、少しだけ俯いて、何かに納得したように
「上がって、飲んでいきな」
最初の幾時かは遊女達全員で宴会のような事をし、八重は新入りの子などに
楽器や歌を教えたりしつつ、笛を吹いたり過ごし
夕刻に差し掛かる頃、しんみりと二人だけで杯を交わした。
「楽しかったよ、あんなに騒いだの何年ぶりかな」
「ああ、アタシもなんていうか、情に流されちまったよ
あの子達にアンタとはこれっきりになるかも知れないなんて言えやしない」
「元々、私は時々ここの手伝いをするだけのただの常連だからね」
「色々教えて、恩を売ったつもりがふと気付いたら借りっぱなしさ」
「そんな事、気にしないでくれ、借りも貸しもキッチリ等分になるのは
縁が切れた時だと言ったのは姐さんだ、それに私からするとまだ私の借りの方が多い」
「はは…、そうなんだよねぇ、この際だ、本音を言うけれどさ
…アタシが死ぬまで、アンタとの縁は切りたくなかったねぇ」
「嬉しいが…そもそも私は祓いだ…そうだ、姐さん、これを見てくれ」
八重がまた上半身の着物を脱ぐ、嵯峨丸は知っているが姐さんは知らなかったな、と。
「アンタの世界はついて行けないよ、ホント、無事を祈って待つだけの生活なんて
真っ平御免なんだよ、でも…」
「おっと、姐さん」
八重は少しだけ姐さんを寄せて額を合わせ
「言えなかったら一生後悔する、さようならだ」
「いつか何かの巡り合わせで、また逢えたらいいねぇ」
「それは願いたいところだな、じゃあ」
「せめて目的は遂げてお呉れよ」
八重は部屋から出かかったのを振り向く、その目は力強く不敵に微笑みながら
「それは必ず!」
◇
その晩、八重はいつにも増して激しく稜威雌を愛した。
ひとしきり済んで、落ち着いた頃に床に横たわる稜威雌が
とびきりに切ない目で八重を見上げた。
「八重様…」
「私は勝つよ、それ以外にないからね」
「私は所詮武器です、八重様はこの刀を後生大事にするが余り
その身に傷跡が増えてゆく…もし、私と引き替えに掴める勝利があるなら…」
「そんな事は言わないでくれ、お前は私の命だ、それに
お前は私の切り札なんだ、ここぞと言う時に、ここだというその時に使う為の」
「…」
稜威雌はその身を八重に寄せた。
「私に力を与えてお呉れ、稜威雌、その為にその顔を上げてお呉れ」
「…私は…貴女に…きっと勝利を」
「そうだ、お前のその心が私を更に強くするんだ」
いつもの感じに戻り、また一通り二人は燃え上がった。
◇
「いつ陣痛が来てもおかしくない所まで来た」
朝、まだ嵯峨丸の容態に変化はないが、八重は「その時が来た」事を告げた。
そこへ母紗代が一度席を外し、大量の握り飯を運んできて
「先ずはみんな、食べて、しっかりと。
手伝いの人にはとにかく何があってもご飯の用意だけはさせる、
ちょっとした隙を伺って、詰め込むのでも先ずはここからよ」
具も数種類入っていて漬物と共に皆ががっつく中、八重はその幾つかを
小皿に避けて漬物も添えて、その皿を大丸に渡して首の動きで行動を促した。
あ、そうか、とばかりに八重に頭を下げ大丸はその小皿を持って庭に、
そしてその塀の上に
「ばーちゃん、食いなよ」
「魔は特にこう言う物食わなくても死にはしないよ」
「食えない訳じゃあないんだろ、食ってくれ」
大丸の視線、純粋に梅に食べて欲しいというその視線、
まぶしすぎてそれだけで魔としての力が弱まりそうだったが、イヤな気はしない。
「…じゃ、いただくよ、どれくらいぶりかね、握り飯なんて」
「沢山食ってくれ、そして宜しく頼む」
「改めて言われなくたってキチンとやる事はやるよ」
大丸はあくまで態度に棘のある梅の様子に、でも凄く満足した様子で戻ってゆく。
いつもと変わらぬ朝のようで、着々と全てが進みある一点に向かっている。
食事後も八重は軽く、疲れ切らないように出来る指導は最後までやった。
そして、そろそろ夕刻になろうとした時だ。
嵯峨丸に陣痛が始まった。
「…少々難産になるかも知れないな、初産だし何しろ元々女として生まれた訳でも無い」
八重が詞で少しその嵯峨丸の痛みや緊張する筋肉をほぐしつつ、
縁側から庭に出て満開になりつつある桜と黄昏に染まる空を見て
「よし、矢張りこの時、どんどん魔が押し寄せてくるぞ…
各地では戦いも始まっているだろう、眠いなんて欲求は許されないぞ
嵯峨丸が子を産み、その産声を上げるまでが戦いだ」
その言葉と、確かに迫る魔の気配に淡女は小皿に乱暴に握り飯を盛り、
そして沙緒理を抱えて屋根まで跳んだ。
八重は弓を構え、矢は祓いで煌々と青い光を滾らせていた。
「沙緒理、私達は八重様の反対側だ」
「はい…!」
母も父も八重とは反対側に出て父は鳥居のギリギリで出迎え
そして大丸は、嵯峨丸に微笑みかけ、狼になり機動力を活かして基本左右、
ただし八重や梅は余力や流れで何処へも動くので、大丸は更にそのフォロー、
目視で見える範囲にまでやって来たおびただしい魔に対し、
八重が祓いの矢を射た、戦いは始まった…!
第十二幕 閉
戻る 第一幕 第二幕 第三幕 第四幕 第五幕 第六幕
第七幕 第八幕 第九幕 第十幕 第十一幕
第十三幕へ進む。